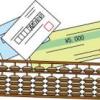医療費控除のありがちな失敗その1~補てんされる金額の計算式~
医療費控除ってとてもめんどくさそうだし、計算しなくちゃいけないし、そもそも何をどうしていいのかワカラナイ、という方も多いと思います。
そこで、医療費控除を申告するにあたり、間違いやすい項目をシリーズでお届けします。
これさえ分かれば医療費控除は怖くない♪
間違いやすい計算式
国税庁のHPでは、医療費控除の対象となる金額の計算式は、以下のようになっています。
実際に支払った医療費の合計額ー保険金などで補てんされる金額ー10万円(またはその年の総所得額が200万円未満の人は、総所得額金額等5%の金額)
しかしこの計算式を素直に当てはめてしまうと、間違えてしまうという恐ろしい結果になります。
ポイントは、保険金などで補てんされる金額の引き方。
× (医療費全体)ー(保険金などで補てんされる金額)
○ (保険金などで補てん対象となった医療費の金額)ー(保険金などで補てんされた金額)
ここがすごくありがちな間違いポイントです。
例:出産入院で50万円、その他の医療費(妊婦健診や夫の医療費など)で12万円かかり、補てんされた金額が57万円だった場合(補てんされた金額=出産一時金42万円+付加金15万円)
夫またはご自身で加入している健康保険では出産一時金に付加金をつけてくれるところがありますよね。
または、加入している保険会社から保険が下りることもあるかもしれません。
補てんされた金額が多いと、素直に計算式に当てはめてしまった場合、医療費控除の最低額である10万円に届かないこともあります。
この場合の計算式は以下のようになります。
× (50万+12万)-57万-10万=-5万円=0円
○ {(50万-57万)=-7万=0円(マイナスは0円とします)}+12万-10万=2万円
医療費を全て合わせてから補てん分を引いた場合、医療費控除対象額は5万円になり、申告対象の10万円に届かないことになってしまいます。
ここで「出産一時金をたくさんもらったし、医療費控除できなくても仕方ない・・・」と思ってあきらめてしまう方もいらっしゃるようです。
でも、本来であれば補填された金額を引くべきなのは、その対象となった医療費のみです。
出産入院に関して補填された金額は、出産入院にかかった費用からのみ引くんですね。
引いてマイナスになった分は0円としますので、出産入院に関しては医療費控除はできませんが、その他にかかった妊婦健診費や夫の医療費など合計が12万円となるので、医療費控除の対象として申告できることになります。
このように、医療費控除は一つ引くところを間違えただけで結果は大きく変わってきます。
せっかくのお金を取り戻すチャンスですので、後悔のないようにしたいですね。
■こちらの記事もおすすめです■
・退職ママ必見!10万円未満で医療費控除が受けられるケースも!
*ランキングに参加しています*