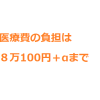出産育児一時金の得するもらい方
出産育児一時金とは、どういう制度なのでしょうか。
申請方法や、得する受け取り方、注意点など、詳しく説明します。
出産育児一時金とは
ご存知のように、分娩には健康保険が使えません。実費負担となりますので、その分娩費として、子供1人につき42万円を補助する制度です。妊娠4か月(85日)以上で出産した場合に適用され、多胎の場合は42万円×人数分が受け取れます。
また、受け取りには「直接支払制度」と「産後申請方式」があります。
いつ、どこでもらえるの?
まずは、自分がどの健康保険に加入しているか確認します。専業ママや仕事を退職し、夫の扶養に入るママなら、夫の加入する健康保険からもらえますし、働くママや保険を任意継続した退職ママは、自分が加入している健康保険からもらえます。
直接支払制度の場合
まずは、出産予定の産院が「直接支払制度」を導入しているか確認します。導入していたら、分娩予約から入院までの間に、産院から「直接支払制度」の合意書をもらって、記入後に提出します。
出産入院時に健康保険証を提出し、出産後の退院時に42万円を超過した分を窓口で支払います。もし42万円より少ない場合は、差額分を健康保険に請求することができます。
産後申請方式の場合
健康保険から「出産育児一時金支払申請書」を取り寄せ、記入しておきます。そして出産入院時に申請書を持っていき、退院までに産院から出生証明欄に記入してもらいます。
退院時は出産費用を全額自己負担で支払い、退院後、申請書を健康保険に提出すると、指定口座に42万円が振り込まれます。
みんな同じ金額?
出産育児一時金は子供1人につき42万円ですが、加入している健康保険によっては、独自の給付(付加金)を付けているところもあります。
そのため、出産により仕事を退職するママは、自分の健康保険と、ダンナさんの健康保険の家族出産育児一時金の給付内容を確認して、よりおトクな方に加入するほうがいいと思います。
私は一人目出産時に仕事を退職しましたが、夫の健康保険に比べて私が入っていた健康保険の方が出産手当金なども多く出たので、夫の扶養には入らず、任意継続にしました。
注意点は?
産院や分娩日時によって分娩費用は異なります。42万円でお釣りがくるケースがあれば、42万円では足りずに、自己負担となってしまうケースも。産院では、事前に予約金を支払わなくてはいけないところもありますので、現金の準備は必要になりそうです。
出産育児一時金をよりお得にする裏ワザ
最近の産院では、クレジットカード払いOKの産院も多くなってきました。
本来は42万円しか使えない出産育児一時金ですが、産後申請方式を利用して、クレジットカード一括払いとしたら、42万円+クレジットカードのポイント分がもらえることになります。
その際は、出産育児一時金の入金がクレジットの引き落としに間に合うように、申請書の提出はお早めに^^
■こちらの記事もおすすめです■
・児童手当
*ランキングに参加しています*